ー家出ー
国鉄時代からだが、JRも社宅でペット飼育は原則禁止である。それとは別に子供たちの学校、家庭の事情これありで、パパさんは仙台の新職場へは単身赴任だった。
盛岡から仙台へ単身赴任して、一ケ月位過ぎたある日、マリオが家出をして帰ってこなくなった。
一歳になったばかりのマリオは幼さを残しつつも、人間に例えると二〇歳そこそこの恋の季節を迎えていた。
マリオは真っ白な長毛のため、外に出すと汚れるという理由で出入り口の戸という戸はピチッと閉められ室内監禁状態だった。
しかし、このことは飼っている人間の勝手な理屈で、マリオには猫の人権(猫権?)としても生理的にもはなはだ迷惑なことだった。
押さえがたい恋情を訴えて夜通し泣き明かして、家族全員に「ウルサイ!」と怒鳴られる。誰一人として、マリオの生理的要求を理解して外出させる気配は全然なかった。
家族も毎夜毎夜、マリオの恋狂いの泣き声で寝不足気味である。
しかし、マリオは誇り高きペルシァ猫族のDNAによる種の保存命令と相まって、ますますつのる本能的な問題解決のため、家族の罵倒に耐えながら真夜中のオペラ歌手さながらに恋情を訴え続けた。
通常、猫には年二回の恋の解禁期間がある。夜な夜な、家の回りはいうに及ばず、風に乗ってくる猫族(特に雌猫)の恋の呼び声や囁きを聞きながら、悶々とした日々を過ごさなければならない焦りは気が狂わんばかりだった。
チャンスはさりげなく訪れた。居間から庭に出るテラス戸がほんの少し開いていた。開いていたといっても、実際は閉まっているに等しい状態で五ミリ位締め残しがあった。ママさんが庭の菜園から夕食のアスパラを調達した後のことである。
この戸はアルミ製の引き戸で、床から天井までの一枚ガラスの数十キロの重い戸で人間でも開け応えのあるものだったが、そこは本能の馬鹿力を発揮して五ミリの隙間に爪を差し込んで渾身の力で戸を開けた。脱出には五センチも開けば充分だった。
庭の木々の匂い。土の心地好い感触。
それに増して黄昏どきの甘ったるい自由な外気の雰囲気がなんともいえなかった。
そのころ、家はてんやわんや。
「アレ! マリオがいない」
「アッ! 外にでたな」
「戸が開いてる」
「お母さんでしょう?」
「私、キチンと閉めたよ!」
そんなやりとりが数分あった後、夕食そっちのけで家族全員による大捜索隊が繰りだされた。
「マリオ!」「マリちゃん」「マーリ」「マリ、マリ」あらゆる呼び方で捜し求める家族一同の声を尻目にして、恋の予感の逃避行に胸躍らせて踏みだした。
ところが、現実は厳しく逃亡初日、家から数十メートルの公園で深夜行われた猫集会で、その洗礼を受けた。
集会に集まった猫は野良猫を筆頭に、普段は自宅と世間を自由に往来している猫族で、箱入り状態で育ったマリオの感覚と異なるものだった。
それでも夢にまで見ていた自由な雰囲気に誘われて、同族の集まりに親愛の情をこめて近づいた。その瞬間、考えられない罵倒を浴びたのである。
「なんだ、お前は」
「どこから来た」
「猫なら、猫らしい格好をしろ」
「誰か、こいつを見たことがあるか」
「何だ、お前の顔は」
「ふん、無視しろ」
そこにひときわ威風のある片方の目が黒い斑状の猫がやってきた。戦国武将伊達政宗のような風貌のボスである。
「おい、おい、そんなのを相手に何を騒いでいるんだ」
散々、雑言を浴びていたマリオのまわりがシーンとなった。
マリオはそのボス猫の威圧感に対し、恐怖を感じて幼いながら威嚇を発した。途端、顔面に強烈な衝撃を受けた。
「ニャン!」と悲鳴をあげて、顔をあげたら先程まで周りにいた仲間達は居なくなっていた。
仲間に無視されたマリオは途方に暮れていた。(どうも家の中で考えていたようにいかないようだ)
その夜は、よその家の床下に潜り込んで過ごした。朝になると空腹で堪らない。「何か食べなくては」と思うが、何もない。空腹を抱えて、人目を避けながらうろうろしているうちにまた夜になった。あちらこちらで恋の叫び声がする。
空腹を忘れて声の方向に向かう。相手は雄だった。知らぬふりをして別な声に向かう。今度は幸運に雌猫である。マリオは声にならない声をあげて近づいた。
通常、猫社会の恋愛成立の条件は雌に雄猫の選択権があり、嫌いな雄は相手にしない。
特に、マリオのようなようやく成猫になったばかりの雄は対象外である。三~六才ぐらいの逞しく闘争心のある雄が好まれる。
これは動物の世界では当然のことであり、丈夫な子を生むための本能的な選択である。人間社会の顔の善し悪しは問題外だ。
当然のことながら、マリオは一蹴された。それでも懲りずに近づくと、物凄い形相で攻撃された。痛いというより、びっくりして逃げ出した。そんなことが二~三日続いた。
空腹はゴミあさりをしたり、飼い犬が散歩している隙を見て、食べ残しの餌を失敬したりしてしのいだ。
家の朝昼晩と三食付きだった生活に比べると、食うや食わずの家出生活は過酷なものだった。それでもマリオは監禁同然の生活より満足していた。
家出して一週間過ぎた頃、マリオの自由を謳歌している気持ちとは関わりなく、そんな放浪生活がヒョンなことで解消した。
夕方ある家の庭先をうろついていると、その家のパパさんらしい人間が声をかけて餌を置いてくれた。空腹だったマリオは警戒心を忘れてガツガツと食べ出した。その途端、首をヒョイと捕まれた。
「おい、捕まえたよ」と言ってその家に連れこまれた。
それから、他家での幽閉生活が始まった。
育った家とは雰囲気も家族構成も段違いで、若いパパさん、ママさんに、三才位の女の子とようやく歩き始めた一才の男の子がいた。女の子は縫いぐるみと勘違いしたのか、荒っぽい動作でマリオを扱った。
さらにひどいのは男の子で、マリオにとっては理不尽そのものだった。殴る、蹴る、玩具で叩く、尻尾をつかんで振り回すで、反抗するとパパさんかママさんに叩かれた。食事は有り難かったが、まことに居心地の悪いものだった。
幽閉のおかげで体力も回復し、消える事のない本能もあって、再び脱走をうかがう日々が続いた。
三日目にチャンスは訪れた。外にいたパパさんと室内の女の子の話しに行き違いがあった。「パパ、嫌い」と言われたパパさんはそれを解消するために戸を開けた。それがチャンスだった。戸の横に寝そべっていたマリオは瞬間的に飛び出した。
「アッ、白」という言葉を後に、再び自由と満たされる筈のない恋の可能性に向けて一目散に走った。
放浪は相変わらず厳しかった。雌猫には相手にされず、雄猫には威嚇され、恋の収穫ゼロの毎日である。勿論、まともな餌はない。
十日を過ぎたある夜、雌猫と雄猫が二匹いる場面に出会った。
マリオは意を決した。雄猫を無視して、雌猫に近づいて愛をささやいた。途端、隣にいた雄猫が「シャーッ」と威嚇を発した。マリオも負けずに「シャーッ」と返した。喉の奥から唸り声を絞りだしながら睨み合いが続く。
尻尾を後ろ足の間にはさんで、前足と後ろ足を踏ん張って睨んでいると、相手が横に動いた。その瞬間、飛び掛かった。
お互い首筋を狙った噛み合いが始まる。組んずほぐれつの格闘は何秒か続いたが、マリオには弱点があった。太く長い尾である。
三度目の格闘の時、尾を噛まれた。万事休すだった。激痛に悲鳴をあげた。痛みを引きずって敗退せざるをえない。
それから、何日か知らない家の縁の下で尾の傷を舐めながら過ごした。
マリオの恋の状況は一向に好転しなかった。空腹を抱えて、途方にくれながら家族を思い出していた。
放浪は一度も恋が成就することのない失恋物語で幕を閉じようとしていた。






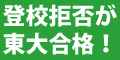
0 件のコメント:
コメントを投稿